着物でお出かけしたい人気スポット!浅草・鎌倉・京都などエリア別に紹介

5. 季節別 着物でお出かけする際の服装のポイント
着物は、日本の美しい四季を表現するのに最適な衣類です。季節に合わせた色や柄、素材を選ぶことで、お出かけがより一層思い出深いものになります。ここでは、季節ごとの着こなしの要点をご紹介いたします。
5.1 春におすすめの着物コーデ
草木が芽吹き、暖かな日差しが心地よい春(3月〜5月)には、心が華やぐような装いが似合います。基本的には裏地の付いた「袷(あわせ)」の着物を選びます。桜色や若草色、藤色といった柔らかなパステルカラーを取り入れると、春らしい雰囲気を演出できます。柄は、桜や梅、牡丹、蝶など、春の訪れを感じさせるものがおすすめです。
日中は暖かくても朝晩は冷え込むことがあるため、温度調節ができる羽織やショールを一枚お持ちになると安心です。浅草の隅田公園の桜並木などを散策する際にも、軽やかな羽織姿は美しく映えます。
5.2 夏におすすめの着物や浴衣
日差しが強くなる夏(6月〜8月)は、涼しさを重視した装いが求められます。6月は裏地のない「単衣(ひとえ)」の着物、最も暑い7月と8月には、絽(ろ)や紗(しゃ)、麻といった風通しの良い「薄物(うすもの)」と呼ばれる着物を着用するのが一般的です。
また、夏といえば浴衣の季節です。花火大会や夏祭りだけでなく、日中の散策にも気軽にお召しいただけます。色合いは白地や紺地、水色など涼やかなものが好まれ、朝顔や金魚、流水紋といった柄が季節感を高めます。強い日差しを避けるための日傘や、涼をとるための扇子は、夏の着物姿に欠かせない小物です。
5.3 秋におすすめの着物コーデ
過ごしやすい気候が続く秋(9月〜11月)は、着物でのお出かけに最適な季節です。9月は単衣、気候が涼しくなる10月からは春と同じく袷の着物へと衣替えをします。からし色やえんじ色、深緑といった、落ち着いた深みのある「こっくりカラー」が、紅葉の景色によく馴染みます。
柄には、紅葉や菊、桔梗、ぶどう、月など、秋の風情を感じさせるものを選ぶと素敵です。春と同様に、朝晩の気温差に備えて羽織やショールをご用意ください。色づく木々を背景に、しっとりとした秋の装いをお楽しみいただけます。
5.4 冬の着物お出かけと防寒対策
空気が澄み、凛とした雰囲気に包まれる冬(12月〜2月)のお出かけでは、寒さ対策が最も重要です。着物は袷を選び、見えない部分や小物で工夫を凝らして暖かくお過ごしください。特に浅草寺への初詣など、屋外に長く滞在する際は万全の準備が欠かせません。
具体的な防寒対策として、次のようなアイテムが役立ちます。
| 場所 | 防寒アイテムの例 | ポイント |
|---|---|---|
| 首元 | マフラー、ファー素材のショール | 顔周りを華やかに見せつつ、冷たい風を防ぎます。 |
| 上半身 | 道行(みちゆき)コート、機能性インナー | 衿元から見えないVネックやUネックの保温インナーを着用します。着物専用のコートは見た目も美しく、高い防寒性を備えています。 |
| 手元 | 肘まである長い手袋 | 着物の袖口から入る冷気を防ぎ、指先まで暖かく保ちます。 |
| 足元 | 足袋インナー、別珍(べっちん)足袋、防寒草履 | 足袋を重ね履きしたり、裏起毛の足袋を選んだりすることで、底冷えから足を守ります。 |
| その他 | 貼るタイプのカイロ | 腰や背中など、冷えやすい場所に貼ると全身が温まります。 |
6. 初心者でも安心 着物でお出かけする時の持ち物と注意点
初めて着物でお出かけする際は、何かと不安がつきものです。しかし、事前に持ち物や着物ならではの立ち居振る舞いを知っておけば、心配は大きく和らぎます。ここでは、初心者の方が安心して着物でのお出かけを楽しめるよう、便利な持ち物と心得ておきたい注意点をご紹介いたします。
6.1 着物でのお出かけであると便利な持ち物リスト
着物姿に合う小さなバッグでも、工夫次第で必要なものを持ち運べます。特にレンタルを利用する場合、最低限の貴重品以外は預かってもらえることもありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
| 持ち物 | 用途・ポイント |
|---|---|
| 小さめのバッグ(巾着など) | 着物の雰囲気に合うものを選びます。スマートフォンや小さめのお財布など、必要最低限のものが入る大きさで十分です。 |
| エコバッグ・サブバッグ | お土産などで荷物が増えた際に重宝します。小さく折りたためるものをバッグに忍ばせておくと安心です。 |
| ハンカチ・手ぬぐい | 手を拭くだけでなく、食事の際に膝にかけたり、少し汚れた場所へ座る時に敷いたりと、一枚あると何かと役立ちます。 |
| 絆創膏 | 履き慣れない草履で鼻緒ずれを起こしてしまうことがあります。万が一の時のために持っておくと、散策を心置きなく楽しめます。 |
| 洗濯ばさみ(クリップ) | お手洗いに行く際に、長い袖を留めておくのに非常に便利です。帯などに挟んでおけば、袖が汚れるのを防げます。 |
| モバイルバッテリー | 写真撮影や地図の確認などで、スマートフォンの電池は意外と早く消耗します。一つ持っておくと安心感が違います。 |
6.2 知っておきたい着物での所作とマナー
着物を着た時の立ち居振る舞いを少し意識するだけで、着崩れを防ぎ、より一層美しく見えます。難しいことはありませんので、基本的なポイントを押さえておきましょう。
〇 美しい歩き方と階段の上り下り
着物での歩き方の基本は、歩幅を小さく、やや内股気味に歩くことです。すり足に近いイメージで歩くと、裾が乱れにくく上品な印象になります。階段を上り下りする際は、裾を踏んでしまったり汚してしまったりしないよう、右手で上前(着物の正面で上になっている部分)の裾を少しだけ持ち上げるとスムーズです。
〇 食事の際の注意点
お食事の際は、長い袖がお皿に触れないように注意が必要です。料理を取る際には、空いている方の手で袖口を軽く押さえると、袖を汚す心配がありません。また、ナプキン代わりとして大判のハンカチを膝の上に広げておくと、食べこぼしで着物を汚すのを防げます。背筋を伸ばし、器を手に持って口へ運ぶと、より美しい姿に見えます。
〇 お手洗い トイレの行き方
着物でのお手洗いは、手順さえ覚えてしまえば決して難しくありません。慌てず、一枚ずつ丁寧に行うのがコツです。
- まず、袖が床につかないよう、洗濯ばさみで帯に留めるか、両袖を前で軽く結びます。
- 次に、着物の裾を上前(うわまえ)、下前(したまえ)の順に一枚ずつめくり上げます。
- 長襦袢、肌襦袢(裾除け)も同様に、汚れないように一枚ずつたくし上げ、すべてを帯と体の間に挟み込むか、片手でしっかりと押さえます。
- 用を足した後は、逆の順番でゆっくりと裾を下ろしていきます。最後に、おはしょりなどが乱れていないか、鏡で確認しましょう。
8. まとめ
着物でのお出かけは、いつもの景色を特別なものに変えてくれる素晴らしい体験です。浅草のような歴史ある街並みを和装で歩けば、心に残る思い出が作れることでしょう。この記事でご紹介したスポット選びのポイントや季節に合わせた装い、便利な持ち物や美しい所作を参考にすれば、初心者の方でも安心して一日を過ごせます。レンタルを上手に活用し、非日常のひとときを心ゆくまでお楽しみください。
都鳥について
1950年の創業以来、都鳥では一貫して本格的な芸者遊びをご提供してまいりました。
芸者歴55年以上の元芸者の女将がいるのは、浅草でも都鳥だけ。
本物の芸者文化を、どうぞ都鳥でご体験ください。
https://miyakodori-geisha.com/






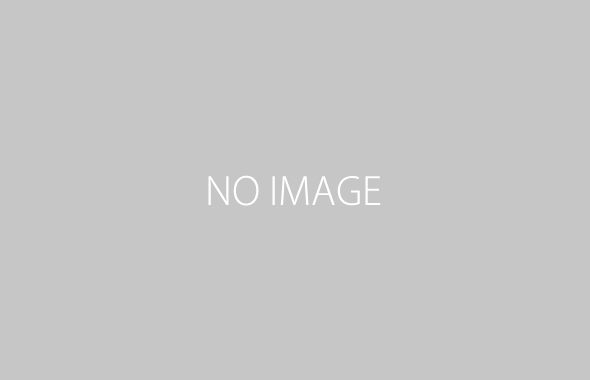





この記事へのコメントはありません。